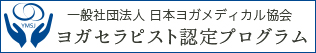■ヨガセラピーと一般的なヨガの違いとは?
ヨガと聞くと、柔軟性を高めたり、リラックスしたりするイメージを持つ方が多いかもしれません。確かに、一般的なヨガも心と体に良い影響を与えますが、ヨガセラピー(ヨガ療法)は、より深く個々の心身の状態に寄り添い、科学的根拠に基づいて行われるアプローチです。
ヨガセラピーの特徴 🌿
✅ 個々のニーズに合わせたアプローチ
ヨガセラピーでは、一人ひとりの体調やライフステージ、健康課題に応じた指導を行います。肩こりや腰痛といった身体の不調だけでなく、不安やストレス、慢性疾患などにもアプローチできるのが特徴です。
✅ 医学・心理学との融合
解剖学・生理学・心理学などの知識を活かし、心と体のバランスを整えることを目的としています。例えば、自律神経の調整やホルモンバランスのサポート、うつ症状や不眠へのアプローチなど、医療的な視点を取り入れた実践が可能です。
✅ 「治す」ではなく「ととのえる」
ヨガセラピーは病気を直接治療するものではありませんが、人が本来持つ自然治癒力を引き出し、心身の調和を促すことを目指します。医療と併用することで、健康維持や回復をサポートする役割を果たします。
✅ 年齢や運動経験を問わず実践できる
一般的なヨガは、体を大きく動かすポーズが多いですが、ヨガセラピーでは呼吸法や瞑想、優しい動きを重視するため、年齢や体力に関係なく取り組めます。初心者や身体に制限がある方でも安心して学ぶことができます。
ヨガセラピーを学ぶことで得られるもの 🌱
・クライアントの心身の状態を深く理解し、適切な指導ができる力
・健康維持や回復をサポートする知識と実践力
・医療・福祉・介護の現場で活かせるスキル
・自身の心身のバランスを整える実践法
より多くの人の健康を支えたい、人に寄り添い支え、喜びを分かち合えるやりがいのある仕事がしたい、ヨガをもっと深く学びたいという方にとって、ヨガセラピーは大きな可能性をもたらします。
■日本ヨガメディカル協会
日本で唯一のIAYTメンバースクールである当協会(一般社団法人ヨガメディカル協会)では、国内で数少ないIAYT認定国際ヨガセラピスト2名を擁し、医療、介護、福祉の現場で安全にヨガを指導できる知識と技術を有したヨガセラピストの育成を目指しています。
現在多くのヨガスタジオで教えられているヨガは、無理をして行えばむしろ健康被害をもたらすこともあります。
協会でお伝えするヨガセラピーは「呼吸ができる人ならだれでもできるヨガ」をコンセプトに、健康な人はもちろん、治療中、治療後の方や、年齢を重ねた人にも安全で十分な健康効果を感じていただけるエビデンスに基づく(医学的に実証された)ヨガとヨガの真髄を、ヨガを教えたことがない方でも、できるだけ短時間で効率的に習得できることを目指して作られたプログラムです。

ヨガメディカル協会の認定プログラム
80名以上の医療従事者が協会のメディカルサポーター
協会では長年理事をお務めいただいている、外科医、免疫学者、漢方医である新見正則先生を始め、がん研有明病院副院長の大野真司先生、国際医療福祉大学大学院の岡 孝和教授、 昭和大学医学部医学教育学講座教授の高宮有介教授、マインドフルネス講座の講師も務めてくださっている精神科医で禅僧の川野野泰周先生など、さまざまな医療分野の80余名の医療従事者の方々が、協会のメディカルサポーターとなって、協会が推奨するヨガセラピーの医療現場への普及の協力と応援をしてくださっています。また、最近では自ら、YMSJ認定ヨガセラピストとなって、病院やクリニックでヨガの普及をしてくださっている医師、看護師の方も増えてきました。
医師も選び学ぶ日本ヨガメディカル協会のヨガセラピー
【医師の視点から見たヨガセラピーの学びとその効果】コロナ禍でご多忙を極める中、日本ヨガメディカル協会で認定ヨガセラピストとなられた3名の現役医師の感想を紹介いたします。
高橋医院 長谷川望院長
Q.ヨガセラピーに興味を持ったきっかけは?
診察室の中だけでは患者さんを元気にすることはできない、と思い特にメンタルケアとしてなにかよい方法はないか、模索していた時に、このメディカルヨガに出会いました。新型コロナとの闘いの中で、コロナが沈静化したあかつきには人と人が交流する場を作りたいと思い、その活動の一環としてヨガを取り入れていこうと思いました。
Q.協会認定コースを修了しての感想
認定コースは講義の内容が充実していてたいへん勉強になりました。
Q.今後、どのようにヨガと関わっていきたいですか?
医院を訪れる患者さんたちはだれしもが明るくグループでいることが好き、ということではありません。ひとりひとりの存在のかけがえのなさを大切にし、それぞれのありのままを受け入れていきたいと思います。人との交わりが負担にならない、それでいて孤立しない、そのような場をつくっていけるとよいな、と思います。
医療法人菅井内科・北野 克宣副院長
Q.ヨガセラピーに興味を持ったきっかけは?
海外では補完代替医療のひとつとしてヨガが高く評価されており、診療に有用だと感じておりました。日本各地の医療関係者の方々が協会のメディカルサポーターをされていることを知り、ヨガセラピーのコンセプトに賛同したからです。
Q.協会認定コースを修了しての感想
岡部代表理事をはじめ、たくさんの素晴らしい講師陣の方々に恵まれ、とても効果的かつ効率的にヨガセラピーのエッセンスを学ぶことができました。わかりやすいテキストと、振り返り動画を繰り返し視聴できたことも良かったです。認定を受けるレポート作成の過程で、なぜヨガセラピーを学ぶのか、今後の診療にどう活かせるのか、自分の考えをまとめることができたのも嬉しい恩恵でした。
Q.今後、どのようにヨガと関わっていきたいですか?
みなさんの笑顔と健幸のために、自分の専門性を最大限活かして貢献したいと願っております。ヨガセラピーはその実現のために必要ですので、様々な場面で啓発と実践に努めます。また自身への慈しみと成長のために、日々マインドフルに取り組み精進して参ります。
竹田内科クリニック 竹田育弘院長
認定後のインタビューより
Q.実際に、先生のクリニックでヨガ教室をひらくことになった経緯を教えてください。
フレイル状態にある方にただリハビリだけを提供しても状態は進行していくといわれています。逆に社会的な活動をしている人、趣味などがある人はリハビリをしなくてもフレイル状態の進行は抑えられるとも言われています。
外来には色々な患者さんが来院されます。元気な患者さんはお幾つになられても活動的に社会参加をされています。その一方で、デーサービスなどに行くことが苦手で、自宅に一人で籠っている患者さんもいらっしゃいます。
クリニックに月一回やってきて私たちと話す以外に人と会話することがないという患者さんがいます。訪問リハビリなどの介入を行っても、フレイル状態が進行していく患者さんに、「私たちに何かできることはないだろうか?」という思いがあり、クリニックでヨガ教室を開催することを検討することになりました。
全文は以下
https://yogatherapy.co.jp/interviews/drtakeda.html
国際基準の質の高いヨガセラピスト認定プログラム
当協会では、アメリカの医療現場で採用されているエビデンスに基づいたヨガセラピーの知識とスキルを効率的に習得できる、二段階の認定プログラムを提供しています。このプログラムは、全米で認知されている国際ヨガセラピスト協会(IAYT)の指導要領に準拠しています。さらに、この学習プログラムは、日本の医療・介護関係者からのフィードバックを取り入れて策定され、具体的なニーズと課題を反映した内容となっています。修了者は、多くの日本の医療従事者からも支持される「日本ヨガメディカル協会認定ヨガセラピスト」としての資格を得られ、信頼度の高いプロフェッショナルとして活躍することができます。
認定ヨガセラピストの学びのステップ
認定プログラムは、ヨガセラピーの専門知識と実践スキルを身につけるための10講座/49時間の包括的なプログラムです(医療従事者の方は6講座/31時間)。ヨガセラピストを目指す方だけでなく、ヨガを通じて自分自身の心と向き合い、より深い自己理解を得たい方にも適した内容となっています。
ベーシックプログラムで学べること
1. ヨガセラピーの基礎を学ぶ
まず、「ヨガセラピー入門講座」では、ヨガセラピーの基本概念、倫理、禁忌(体の状態によって避けるべきヨガのポーズなど)を学び、安全で効果的な指導法を習得します。実技とロールプレイを通じて、どなたにも怪我無く行うことのできるポーズを提供するスキルを身につけます。初心者の方でも安心して学べる内容です。
2. コミュニケーション力の向上
「コミュニケーション講座」では、ノンバイオレントコミュニケーション(非暴力コミュニケーション通称NVC)を学びます。、NVCは、「共感」に基づくコミュニケーション手法であり、対人関係や対話が求められるさまざまな分野でカウンセリングや医療介護など様々な分野で活用されています。相手を尊重しながら適切に伝える力が養われますので、人間関係の質を高め、日常生活にも活かせるスキルを習得できます。また、ヨガセラピーのセッションでは、ストレスやトラウマを抱える方と接する機会が多くあります。NVCを活用してコミュニケーションを行うことで、だれでも安心して参加できるクラスづくりができます。
3. マインドフルネスと心理学的アプローチを取り入れる
精神科医であり禅僧でもある川野泰周先生の「マインドフルネス講座(禅×医療)」では、最新のマインドフルネス研究や禅の視点からのアプローチを学びます。
「森田療法を共に学ぼう」では、感情の法則と精神療法の基礎を習得し、ヨガと心理学の共通点を理解します。森田療法は、不安や恐怖を「あるがまま」に受け入れつつ、目的本位の行動を重視する精神療法です。症状を排除しようとせず、生活に集中することで自然に適応力を高めることを目指します。川野先生のマインドフルネス講座に合わせて学ぶことにより、心の健康をサポートする力を高めるだけでなく、自分自身の心の状態を深く理解し、整える方法を学ぶことができます。
4. 倫理とヨガセラピストとしての在り方を確立する
「ヨガセラピストとしての倫理」では、指導者としての在り方や倫理観を深めます。ディスカッションやペアワークを通じて、実際の現場で起こりうる倫理的課題について考え、適切な対応力を養います。ヨガセラピストを目指さない方にとっても、人との関わり方を見直し、自分自身の生き方を見つめる貴重な学びとなります。
5. マインドフルネスを活用した指導法を学ぶ
「マインドフルネス・ヨガセラピー(MYT)プログラム指導法入門講座」では、マインドフルネスを取り入れたヨガセラピープログラムを実際に体験し、その指導方法を学びます。心身の不調を抱える人に向けた効果的なアプローチを身につけることができます。また、自身の日々のストレスマネジメントや自己成長にも役立つ内容です。
6. 身体の理解を深め、効果的な指導を行う
解剖学の基礎を学ぶ「ヨガセラピーに活かす解剖学1」では、「立つ」「歩く」「座る」といった日常動作を力学的に理解し、適切な身体の使い方を考察します。「ヨガセラピーに活かす解剖学2」では、筋膜とヨガの関係を学びます。筋膜は、姿勢維持や運動補助、感覚伝達、リンパ促進など多くの役割を持ち、近年では自律神経やストレス軽減にも関与すると注目されています。講座では、筋膜の特性を理解し、それを活かしたヨガの実践方法を学びます。これらの講座は、自分自身の身体の使い方を見直し、健康的な動作習慣を身につける機会にもなります。
7. 医療知識を身につけ、専門的な対応力を高める
「医療基礎講座」では、一般的な疾病に関する知識を習得し、ヨガセラピーを医療と結びつける視点を養います。「医療業界の基礎知識」では、医療機関との連携方法や交渉術を学び、ヨガセラピストとしての活動の幅を広げます。医療業界への関心がある方にも有益な講座です。
自分のペースで受講できる
講座は、自分の関心があるところ、スケジュールに合ったものから受講順を問わず自由に学ぶことができます。また、お支払いは、事前の一括納入ではなく各講座ごとのお支払いが可能ですので、5年以内であれば自分のペースで学べます。

【yogatherapy.co.jp】から離れ【ヨガセラピスト認定プログラム】に移動します。