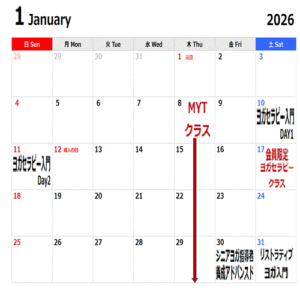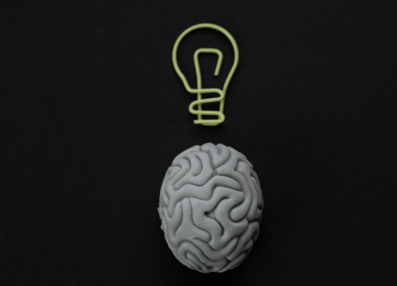

私たちは、何もしていないときでも、頭の中ではさまざまな思考がめぐっています。過去の出来事を思い出したり、未来の心配をしたり、誰かに言われた言葉を反芻したり……。
こうした「心のつぶやき」の状態を、脳の「デフォルト・モード」と言います。「デフォルトモード」という言葉は、パソコン用語では「あらかじめ自動的に設定されている状態」 を意味しますが、脳科学では「脳が“何もしていない時”に自動的に動くモード」という意味で使われます。
脳のデフォルトモードとは──“何もしていない時”の脳の活動
デフォルトモードは、私たちが作業に集中していないとき――つまり、「ぼんやりしている時」に活動する脳のシステムです。人は起きている時間のかなりの割合(30〜50%程度)を、デフォルトモードで過ごしていると言われています。つまり、しょっちゅう心の中で何かをつぶやいている状態ということです。
心のつぶやきの内容は、
- 自分に関する思考(I, me, my)
- 過去の記憶の想起
- 未来への想像
- 他者の気持ちを推測する(共感・mentalizing)
といった、「自己を中心にした思考」が多いと言われています。言い換えれば、私達はぼーっとしている時、何も考えているのではなく、私という物語を語り続けているのです。
電車などで、たまに一人でブツブツと、脈絡のないことを喋り続けている、ちょっと壊れた感じの人を見たことはありませんか?実は私達も、実際に声を出していないだけで、同じようなことをしているわけです。
デフォルトモードは苦しみの源
マインドフルネスや瞑想の世界では、このデフォルトモードが苦しみの源になりやすいと考えられています。
なぜなら、デフォルトモードの状態では、心は「今ここ」から離れ、
- 「あの時、こうすればよかった」過去の後悔
- 「明日うまくいくだろうか」未来への不安
- 「あの人はどう思っているだろう」人間関係の悩み(他者の心の推測)
というような思考を反芻しがちです。こうした思考は、実際には起こっていない「仮想の世界」の中で私たちを消耗させます。その結果、ストレスや不安、自己否定のネガティブループを生み出してしまうのです。
ハーバード大学の神経科学者Judson Brewerはこう述べています:
「デフォルトモードは心がさまようときに働くが、過剰に活性化しているとき、それは幸福な場所ではない。」
脳の休息で静かな空白を味わう
マインドフルネスや瞑想や座禅では、呼吸や身体感覚に注意を戻す練習を通して、この「思考の無限ループ」に気づき、そこから一歩距離を取る力を育てていこうとします。
デフォルトモードを消そうとしたり止めようとするのではなく、思考の無限ループに気づき巻き込まれない練習をします。
脳科学の研究では、瞑想の熟練者は脳のデフォルトモードネットワークを司る部分(内側前頭前皮質、後部帯状皮質、角回)などの活動が弱まり、代わりに「今ここ」に注意を向ける領域(前頭前皮質など)が強化されていることが確認されています。
何かに没頭とした後に「すっきり感」「解放感」「「ととのった感」といった感覚を味わった経験はありませんか?これは、今ここに集中したことで、一時的にデフォルトモードから解放され、雑念がなくなり、脳が休息したために味わうことができる感覚です。心は“静かな空白”を味わうことができるのです。
退屈が生み出す創造性
ハーバード大学の教授で社会科学者の Arthur C. Brooks教授 は、「幸福学(Science of Happiness)」の第一人者のひとりで、彼の講義は学生に大人気で、最近アメリカのメディアでも大きな注目を集めています。彼は、「デフォルトモード」をまったく異なる角度から捉えています。彼はこう語ります:
「心がさまようとき、デフォルトモードが活性化する。──そしてそのときこそ、人生の大きな問いを自分に投げかける。」
つまり、スマートフォンやSNSで常に情報を浴び続け、心がさまよう時間さえ失っている現代において、多くの人が人生の目的を問うこともなく失っていると警鐘を鳴らしています。
Brooksは、「退屈な時間」こそが、
- 人生の意味を考える
- 新しいアイデアをつなぐ
- 深い洞察に出会う
ための創造的な時間だと言っています。Brooksはデフォルトモードは人生の意味とインスピレーションの源泉だと説きます。
アルキメデスが浴槽の中で王冠の純度を測る方法を思いついたり、ニュートンがリンゴの木の下で万有引力の法則にたどり着いたように、脳のデフォルトモードは確かに創造的な時間にもなり得ます。
心の静けさと空想のバランス
マインドフルネスとBrooksの立場は、一見すると正反対に見えますが、相反するものではなく、静けさと空想のバランスが大切なのではないでしょうか。マインドフルや瞑想によって、過去の後悔や未来の心配や自己否定といったネガティブな反芻思考から脳を解放しつつ、「空想の自由」に心を遊ばせる。そのバランスこそが現代を生きる私たちに必要な心の知恵なのかもしれません。
ちょっとした隙間時間にも、すぐにスマホを見てしまう人ばかりの今、私達はお手軽に「退屈」と「デフォルトモードから来る苦しみ」からは解放されたように感じているかもしれませんが、Brooksの言うように実に大きな代償を払っているのかもしれません。
そこでお薦めしたいのが、以前にも書きましたが隙間時間瞑想です。電車やエレベーターや信号を待っているちょっとした時間に、スマホに目を向ける代わりに、肩の力を抜いて、そっと目を瞑って呼吸に意識を向けてみてください。わずかな時間でも、脳が静まり、「静けさ」と「創造性」の両方がゆっくりと戻ってくるのを感じられることでしょう。
隙間時間瞑想のやり方
たった 数十秒でもかまいません。「何かを待っている時間」 がチャンスです。
1. 姿勢をととのえる
- 背筋を軽く伸ばし、肩の力を抜きます。
- 足の裏が床に触れている感覚を感じます。
- 座っていても、立っていても大丈夫です。
ポイントは「ゆるやかな安定感」をつくること。姿勢が整うと、呼吸も自然に深まります。
2. 呼吸に意識を向ける
- 目を閉じるか、または視線をやや下に落とします。
- 吸う息と吐く息を「コントロールしよう」とせず、ただ感じ取ります。
- 吸うときに「空気が体に入ってくる」
- 吐くときに「体から出ていく」
その流れを、観察するように見守ります。
(慣れてきたら、数を数えてもOK)
3秒で吸って、4〜5秒で吐く、くらいが心地よいでしょう。
3. 雑念が出てきたら「戻る」
途中で「あと何分かな」「次の予定は…」などの思考が浮かんでもOK。それに気づいた瞬間、「あ、考えてたな」と優しく気づいて、呼吸に意識を戻す──これだけで瞑想になっています。
瞑想とは「何も考えないこと」ではなく、「気づいて戻る」練習です。最後にひと呼吸、ゆっくりと吐き出しましょう。
文責:Yumiko M.H.