
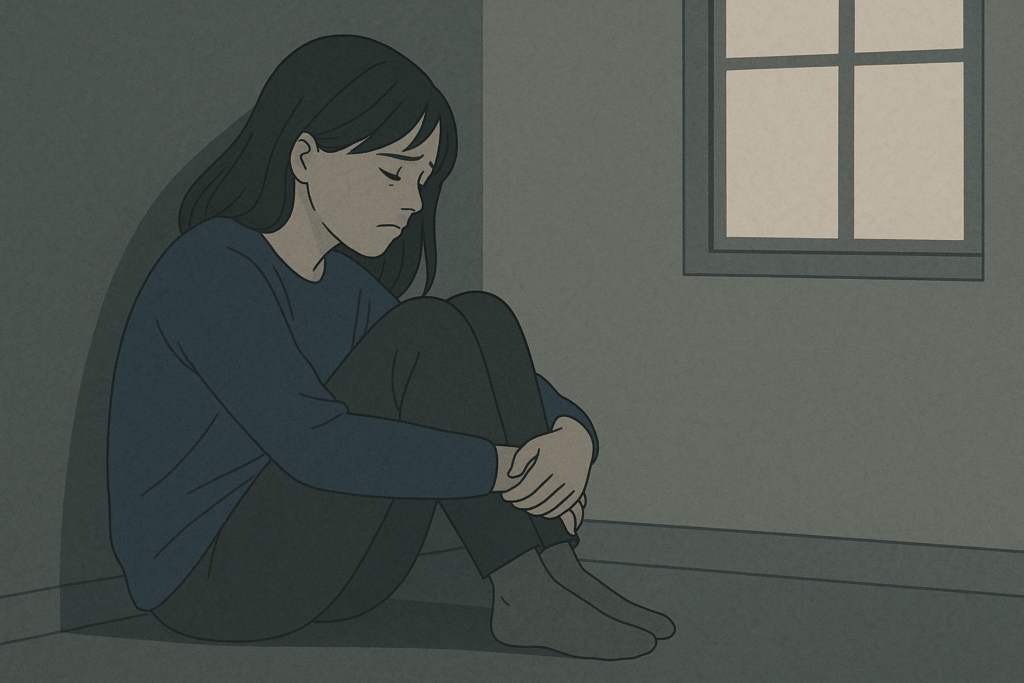
うつ病は安心安全と感じられていない状態での防衛反応
この10数年、注目を集めている自律神経の新理論「ポリヴェーガル理論」(←こちらでかなり詳しく説明しています。)では、「うつ」の状態は「心が弱い」からではなく、自律神経が「安全ではない」と感じている状態だと説明します。
ごく簡単にポリヴェーガル理論を説明すると、自律神経は私たちが「安全」か、「危険」か、そして「命の危険」にさらされているかによって、3つの異なる反応モードを自動的に切り替えています。
①安全が感じられるときには、腹側迷走神経が働き、心拍が落ち着き、呼吸がゆるやかになり、人とのつながりに安心感や温かさを感じられます。
②危険を察知すると、交感神経が優位になり、心拍が速くなり、筋肉が緊張して「戦う」か「逃げる」ための準備をします。
③さらに命の危険を感じるほどの強いストレス下では、背側迷走神経が働き、エネルギーを極端に節約して生き延びるために仮死状態や「力が抜けて動けなくなる」「感じなくなる」というシャットダウン反応が起こります。
これらの反応は全て生命を守るための生存戦略です。
自律神経は、私たちが意図せずとも常に環境や身体内部の変化を評価しており、ポリヴェーガル理論ではこの無意識の安全検知を「ニューロセプション」と呼びます。ニューロセプションによって“安全・危険・生命の危機”が判断され、その状態に応じて自律神経が心身を守るための上記のような反応を自動的に引き起こします。
③のシャットダウンモードの状態とは、スマートフォンに例えるなら、電池残量が5%を切ったときに、なんとかスマホが息絶えないように、必要最小限の機能を残して低電力モードになるようなものです。
人の場合、「無気力・無関心・感情の麻痺・倦怠感・失体感・離人感、引きこもり・社会的つながりの喪失・胃腸の不調」などの形で現れます。
つまり、うつ病は心身が危険を感じて、自らの命を守るための反応なのです。回復の鍵は「気力を振り絞ること」ではなく、安全感(腹側迷走神経の活性化)を取り戻すことにあります。
ポリヴェーガル理論を提唱したポージェス博士は、この安全感を取り戻す方法の一つとして「呼吸を重視するヨガ」を推奨しています。では、なぜヨガがうつの回復に役立つのでしょうか?
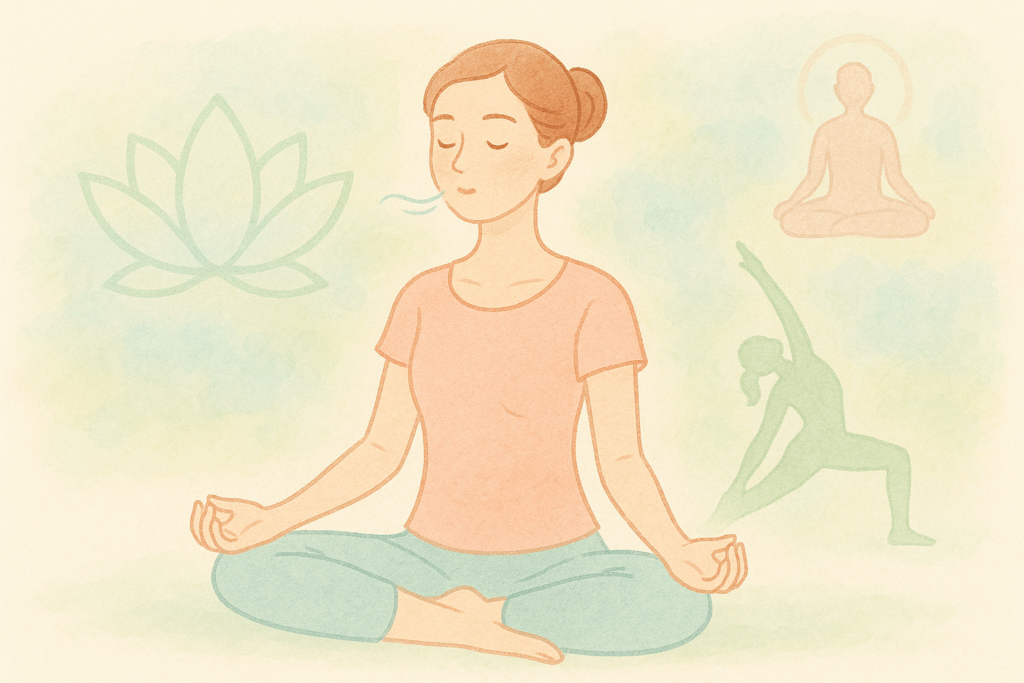
ヨガがなぜ「うつ病」に働くか:メカニズムと理論的背景
世間一般のヨガのイメージは、若くて柔軟性に富んだ細身の女性が、インスタ映えする美しいポーズを決めている姿かもしれません。
しかし本来のヨガは、ポーズの美しさを競うものではなく、「心と身体を調和させるための実践」です。
ヨガの語源「yuj(ユジュ)」には「つなぐ」「調和させる」という意味があり、身体と呼吸、心と感情、そして自分と世界とのつながりを取り戻すことを目指す哲学的な道でもあります。
ヨガには「ゆったりとした呼吸(プラーナヤーマ)」「ポーズ(アーサナ)」「瞑想・意識(ディヤーナ)」が組み込まれ、これらを通して生理的・心理的メカニズムの両面から働きかけることができます。
セラピーとしてのヨガの活用
このような本来のヨガのあり方を大切にすることで、たとえば体が硬くても、年齢を重ねていても、心身の不調があっても、ゆったりと自分のペースと呼吸に合わせて体を動かしていくことで、自律神経は少しずつ防衛反応を解除し、安心感を取り戻していきます。
このプロセスを神経生理学的にざっくりと説明します。
お風呂に入って「は~」とリラックスした状態、「癒される~」と感じている時の呼吸を思い浮かべてみてください。わたしたちは、体と心が「今は安全だ」と感じる時に自然にゆったりと呼吸をします。
呼吸は自律神経によってコントロールされていますが(自律神経によって自動的にコントロールされている体の機能は他に、心拍、血圧、消化、体温調整、膀胱の働き、生殖器の反応など)、唯一、私達人間が意識的にコントロールできるのが呼吸です。ですので、あえて呼吸をゆったりと行うことで、脳は「今、私はストレスや危険を感じていないリラックスモードだ。」というメッセージを受け取り、身体の防衛反応を解除しはじめます。これは、鬱症状に伴う自律神経の過剰な防衛モードを解き、安心と回復のモード(副交感神経優位)へ導く最初の一歩です。
さらに、身体の動きは、呼吸に合わせて体を動かすことで、筋肉や関節、内臓から「安全である」という感覚信号(ボディ・フィードバック)を脳へ送り、身体感覚(interoception)の回復を促します。これは、うつ状態で鈍くなりやすい身体感覚や感情の認知を回復させ、再び「感じる力」を取り戻す助けになります。特に、胸を開くポーズや背骨を動かすポーズは、姿勢の改善だけでなく、呼吸を深め、前向きな感情表現を支える神経経路を活性化します。
一方、瞑想は、過去や未来への思考のループから離れ、「今この瞬間」に意識を戻す練習です。瞑想は、脳の過活動を鎮め、扁桃体(不安や恐怖を司る部位)の反応を穏やかにし、前頭前野(思考と感情のコントロールを担う部位)の働きを回復させることが研究で示されています。これにより、感情の波に巻き込まれにくくなり、自分を客観的に見つめる力が育まれます。
うつ症状の改善においてヨガが有効とされるのは、まさにこの身体・呼吸・心の統合的アプローチによって、神経生理レベルから「安心とつながり」を取り戻していくからなのです。特に私達が伝えているセラピーとしてのヨガ(ヨガセラピー/メディカルヨガ)は、このような神経生理学的な反応を理解した上で、参加される方の心と体の安全に十分に配慮して行われます。
「安心」と感じた時に起こる体の変化
ヨガを続けるうちに、次のような生理的変化が少しずつ積み重なります:
- 生理的変化 感覚としての変化
- 心拍変動(HRV)の上昇→ 呼吸が自然に深くなり、落ち着きを感じる
- 迷走神経トーンの向上→ 消化が改善し、睡眠が深くなる
- 筋緊張の低下→ 体の力みが抜け、軽やかに動ける、痛みが和らぐ
- 扁桃体(恐怖中枢)の過活動低下→ 不安や焦りが和らぎ、安心感が戻る
- コルチゾール(ストレスホルモン)の低下→ 慢性的ストレスの改善
多くの研究のエビデンスの積み重ねの結果、ヨガは単なるリラクゼーションではなく、神経系を整える生理的効果を持つ補助療法として、アメリカの医療機関に取り入れられています。
注意点・留意事項
- 自殺念慮や活動不能、入院が必要な重度のうつ病では、ヨガのみでの改善を目指すのではなく、医療や心理療法と併用することが大切です。
- 一般のヨガ教室は健康な人向けが多いため、セラピー的なヨガを理解しているインストラクターのもとで行うのが安全です。
ただし:うつの状態によっては注意が必要
うつ病が強い状態のとき、マインドフルネスやボディスキャンのように「自分の内側を感じる」練習が、かえって危険になることがあります。その理由も、ポリヴェーガル理論で説明できます。
うつのとき、神経は「シャットダウン(背側迷走神経)」の状態にあることは先に述べました。つまり体と心は生き延びるためのギリギリの選択として、あえて心拍を落としたり血圧を下げたり、心と体を切り離して感じないようにしている状態です。感じること自体が安全でないという状態の時に、身体の感覚や感情を無理に感じようとすると、生き延びるために切り離した感覚や記憶がよみがえったり、さらに心拍が落ちたり、無力感や虚脱感や絶望感が強まることがあります。
そのため、うつ病の初期や強い時期には、内側に注意を向けすぎるよりも、たとえば、足裏を感じる、手をさする、温かさ・重さを感じるなどの、やさしい感覚刺激を通して「感じても大丈夫」という経験を重ねることが先になります。




